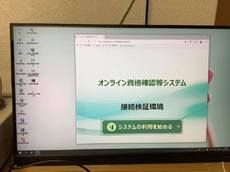2016年11月14日
PACS運用について
一番の問題点は、データのバックアップをどうするか、PC故障に備えてどうするか?という点です。
デジタルデータですので、下手すると、一瞬ですべてを失います。
結局は、故障、トラブルに備えて、全てを二重化するより、仕方ありません。
これでもか!!というぐらい冗長化しておく必要があります。
そうすると、台数が多くなりますので、それぞれ、コンパクトな筐体のPCを用います。おすすめは、スリムケース。
ほとんどの、スリムケースは、光学ドライブ1台、3.5インチベイ1台、2.5インチベイ1台が内臓できます。
このケースを立てて並べて管理します。(HTPCを重ねてもいが、故障したとき面倒)。
NCUも使えますが、CPUがノートPC用の低消費電力CPUなので、同じCore-i5でもデスクトップ用の半分以下の速度しか出ません。
一番の問題点は、データのバックアップをどうするか、PC故障に備えてどうするか?という点です。
デジタルデータですので、下手すると、一瞬ですべてを失います。
結局は、故障、トラブルに備えて、全てを二重化するより、仕方ありません。
これでもか!!というぐらい冗長化しておく必要があります。
そうすると、台数が多くなりますので、それぞれ、コンパクトな筐体のPCを用います。おすすめは、スリムケース。
ほとんどの、スリムケースは、光学ドライブ1台、3.5インチベイ1台、2.5インチベイ1台が内臓できます。
このケースを立てて並べて管理します。(HTPCを重ねてもいが、故障したとき面倒)。
NCUも使えますが、CPUがノートPC用の低消費電力CPUなので、同じCore-i5でもデスクトップ用の半分以下の速度しか出ません。
1)最低でも、サーバーは2台、それぞれに、バックアップ用のHDDを用意すること、できれば、NASも2台。
システムドライブを内蔵SSDに、データドライブを内蔵HDDに、それをバックアップする外付けHDD。外付けHDDのデータをNASにミラーしておく。システムドライブはSSDにしなくても良いのですが、システムとデータは分けておいたほうが便利です。
こうして、全てを2重化すれば、同時に2台壊れることは、まず、ないでしょう。
外付けHDDだけじゃダメなのか?ですが、ダメです。なぜなら、PC本体と繋がっているからです。電気的に。つまり、PCの電源トラブルで、異常電流が流れた場合、道連れになる可能性があります。USB接続の場合、特に、5V500mAの電源電流が流れますから・・・・。NASもケーブルで繋がっていますが、ネットワークケーブルには電源電流は流れていません。そして、間に、ハブが入ります。ですから、PCの電源の影響は無いものと考えられます(雷のサージは別)。
2)予備機はどうするか・・・・
連日運用する事が求められますから、修理にかかる時間が、数時間なら、予備機は無くても大丈夫!!なんて、言うつもりは在りません。自作PCで、OSも自分でインストールですから。慌てて修理すると、ろくなことは無いので、予備機を作っておきましょう。Windows7を再インストールする羽目になると、だいたい、最近でははDVDからインストールして、アップデート終了、ソフトウエアセッティング終了まで2日ぐらいは掛かってしまいますから。おまけにWindowsUpdateがトラブりまくりで、手動インストールしないとアップデートできないことが多々あります。
ケーブル抜いて、機器を入れ替え、ケーブル繋げばOK、というところまで、セッティングしておきましょう。そうすれば、データを復旧するだけで済みます。
さて、これで、運用できますが、もう一台、テスト機が必要です。何かトラブルがあったとき、予備機でテストするわけにもいきません。もう一台、テスト機が無いと、OSのアップデート後の動作確認すらドキドキです。もちろん、予備パーツも用意しないといけません。PC1台組めるだけのパーツをストックしておきましょう。
PACSをフリーソフトで組んで自主運用するということは、メンテも自分でやるということですので、これぐらいの準備はしておかないと、業務で使えません。
しめて、PC4台、予備パーツ1台分、外付けHDD2台、NAS2台。また、HDDは消耗品なので、予備は大目に。
システムドライブを内蔵SSDに、データドライブを内蔵HDDに、それをバックアップする外付けHDD。外付けHDDのデータをNASにミラーしておく。システムドライブはSSDにしなくても良いのですが、システムとデータは分けておいたほうが便利です。
こうして、全てを2重化すれば、同時に2台壊れることは、まず、ないでしょう。
外付けHDDだけじゃダメなのか?ですが、ダメです。なぜなら、PC本体と繋がっているからです。電気的に。つまり、PCの電源トラブルで、異常電流が流れた場合、道連れになる可能性があります。USB接続の場合、特に、5V500mAの電源電流が流れますから・・・・。NASもケーブルで繋がっていますが、ネットワークケーブルには電源電流は流れていません。そして、間に、ハブが入ります。ですから、PCの電源の影響は無いものと考えられます(雷のサージは別)。
2)予備機はどうするか・・・・
連日運用する事が求められますから、修理にかかる時間が、数時間なら、予備機は無くても大丈夫!!なんて、言うつもりは在りません。自作PCで、OSも自分でインストールですから。慌てて修理すると、ろくなことは無いので、予備機を作っておきましょう。Windows7を再インストールする羽目になると、だいたい、最近でははDVDからインストールして、アップデート終了、ソフトウエアセッティング終了まで2日ぐらいは掛かってしまいますから。おまけにWindowsUpdateがトラブりまくりで、手動インストールしないとアップデートできないことが多々あります。
ケーブル抜いて、機器を入れ替え、ケーブル繋げばOK、というところまで、セッティングしておきましょう。そうすれば、データを復旧するだけで済みます。
さて、これで、運用できますが、もう一台、テスト機が必要です。何かトラブルがあったとき、予備機でテストするわけにもいきません。もう一台、テスト機が無いと、OSのアップデート後の動作確認すらドキドキです。もちろん、予備パーツも用意しないといけません。PC1台組めるだけのパーツをストックしておきましょう。
PACSをフリーソフトで組んで自主運用するということは、メンテも自分でやるということですので、これぐらいの準備はしておかないと、業務で使えません。
しめて、PC4台、予備パーツ1台分、外付けHDD2台、NAS2台。また、HDDは消耗品なので、予備は大目に。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。